「借金がどうしても返せない…」「自己破産を考えているけど、何をどうすればいいか分からない…」そうお悩みではありませんか?自己破産は、借金をゼロにして生活を立て直すための最終手段です。しかし、「自己破産」と聞くと、「人生の終わり」といったネガティブなイメージを持つ人も少なくありません。正しい知識を持たないまま不安を抱え続けるのは、精神的にも辛いことです。自己破産は、法律に基づいた正当な手続きであり、人生を再スタートさせるための有効な手段です。
この記事では、自己破産の手続きの流れから、必要書類、そして注意点までを徹底的に解説します。自己破産を検討するあなたが、不安を解消し、正しい選択をするための参考にしてください。
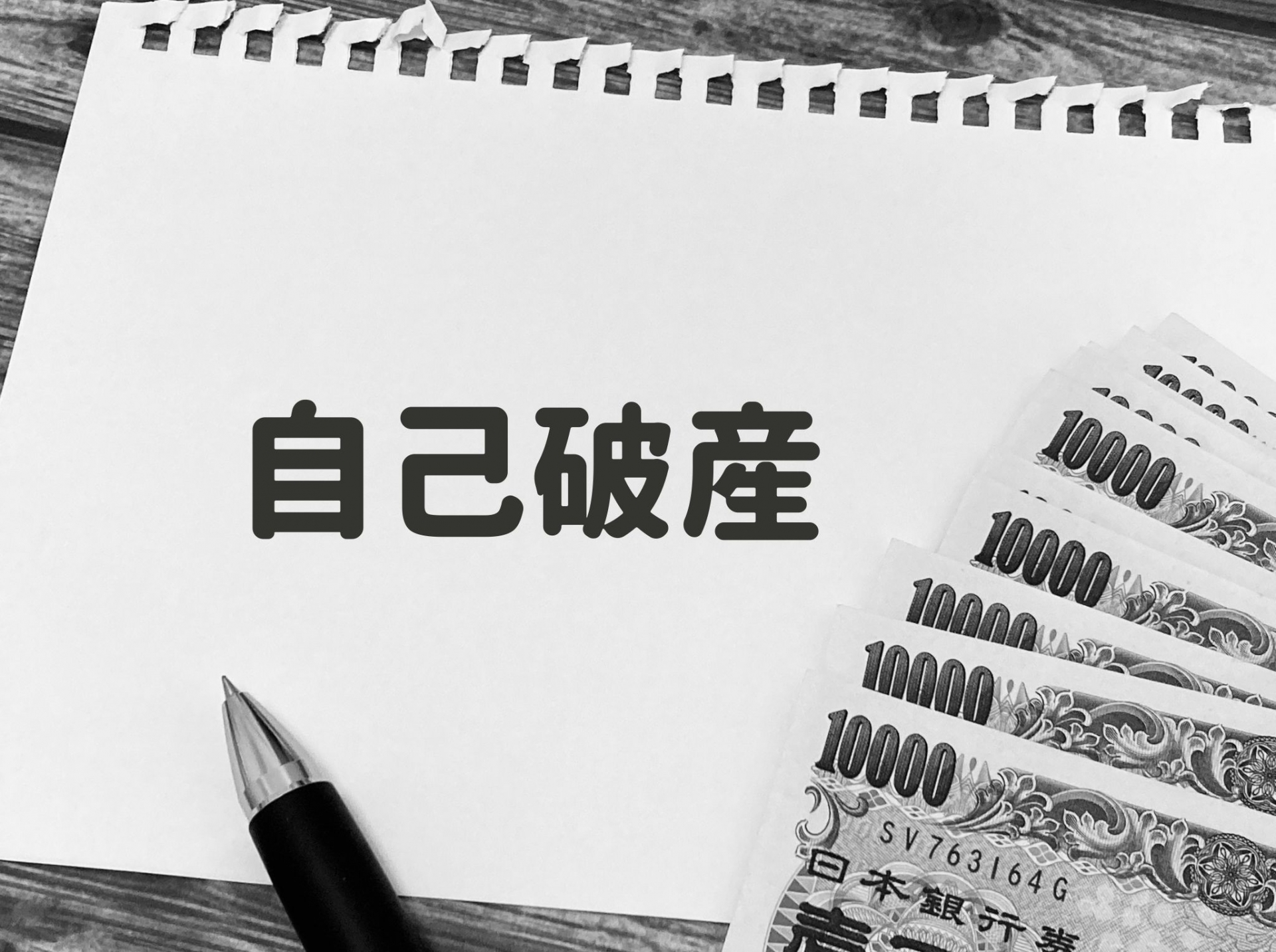 (※イメージ画像)
(※イメージ画像)
自己破産とは?手続きの基本と原則
自己破産とは、裁判所の決定に基づき、借金の返済義務を免除してもらうための法的な手続きです。借金をゼロにすることで、経済的に行き詰まった人が生活を立て直し、社会復帰するための「救済措置」と言えます。
1.自己破産の原則
- 支払い不能: 自己破産は、「支払い不能」の状態であることが認められなければなりません。「支払い不能」とは、借金の総額が、自分の収入や財産では返済しきれない状態を指します。
- 免責許可: 自己破産の手続きが完了すると、「免責」が許可されます。この「免責」が認められることで、借金の返済義務が法的に免除されます。
2.自己破産で手放す財産
- 自己破産をすると、原則として所有している財産は換価・処分され、債権者に公平に分配されます。
- 対象となる財産:
- 持ち家や土地といった不動産
- 20万円以上の価値がある自動車
- 99万円を超える現金
- 高価な貴金属や有価証券など
- 手元に残せる財産: 生活に必要な家具や家電、仕事道具、一定額以下の現金などは、自由財産として手元に残すことができます。
自己破産は、すべての借金をゼロにできる強力な手段ですが、その分、生活に大きな影響を及ぼすため、手続きの流れを正しく理解することが重要です。
自己破産の手続きの流れ5ステップ
自己破産の手続きは、専門家(弁護士など)に依頼するのが一般的です。ここでは、手続きの主な流れを5つのステップに分けて解説します。
ステップ1:専門家への相談と依頼
- まずは弁護士などの専門家に相談し、自分の借金の状況を伝えます。
- 専門家が「支払い不能」の状態か、自己破産が適切かどうかを判断し、依頼を受けると「受任通知」を各債権者に送付します。この時点で、債権者からの督促は全て止まります。
ステップ2:必要書類の準備
- 弁護士の指示に従い、住民票、源泉徴収票、通帳のコピーなど、自己破産の申立てに必要な書類を収集します。
- 専門家が書類を整理し、申立書を作成します。
ステップ3:裁判所への自己破産申立て
- 作成した申立書と必要書類を、債務者の住所地を管轄する地方裁判所に提出します。
- 裁判所が申立書を受理し、審理を開始します。
ステップ4:破産手続きの開始と免責審尋
- 裁判所が破産手続きの開始を決定します。この段階で「破産者」となり、一定の資格制限が生じます。
- 破産管財人が選任される「管財事件」の場合は、財産の調査や換価・処分が行われます。
- 債務者が裁判官から免責の可否について尋ねられる「免責審尋」が行われます。
ステップ5:免責決定と官報への掲載
- 裁判所が「免責」を許可すると、すべての借金の返済義務が免除されます。
- 官報(国が発行する広報誌)に、破産開始決定と免責許可決定が掲載されます。これにより、自己破産の手続きは完了です。
自己破産に必要な書類の準備
自己破産の手続きには、現在の財産状況や生活状況を証明するための多くの書類が必要になります。
1.必ず必要になる書類
- 身分証明書: 運転免許証、健康保険証など。
- 収入に関する書類: 源泉徴収票、給与明細、確定申告書など。
- 住民票: 世帯全員の住民票。
- 家計状況に関する書類: 家計簿、通帳のコピーなど。直近1〜2ヶ月分の家計の収支を証明する書類が必要です。
- 財産に関する書類: 預金通帳、有価証券、不動産の登記簿謄本、自動車の車検証、保険証券など。
2.ケースに応じて必要になる書類
- 退職したばかりの人: 退職証明書、離職票など。
- 住居が賃貸の人: 賃貸借契約書のコピー。
- 年金を受給している人: 年金受給証明書。
必要書類は、ケースによって異なるため、必ず弁護士の指示に従って準備を進めるようにしましょう。専門家が書類収集のサポートも行ってくれるため、一人で悩む必要はありません。
自己破産で注意すべきことと免責不許可事由
自己破産は借金をゼロにできますが、そのデメリットや、免責が認められない「免責不許可事由」について知っておくことが重要です。
1.自己破産のデメリット
- 信用情報への登録: 自己破産の事実は、信用情報機関に事故情報として約5〜10年間登録されます。その間、新たな借入れやクレジットカードの作成ができなくなります。
- 財産の処分: 生活に不可欠なものを除き、一定以上の価値がある財産は処分されます。
- 資格制限: 手続き期間中、一部の職業(弁護士、司法書士、警備員など)に就くことが制限されます。
- 官報への掲載: 氏名や住所が官報に掲載されますが、一般の人が官報を見て破産の事実を知る可能性は低いです。
2.免責不許可事由
- 以下の事由に該当すると、原則として免責が認められません。
- 借金の原因が浪費やギャンブル: 借金が、パチンコや競馬、ブランド品の購入など、無駄な浪費やギャンブルによるものである場合。
- 財産の隠蔽・偽装: 財産を隠したり、意図的に価値を下げたりする行為。
- 特定の債権者への返済: 特定の債権者だけを選んで返済する行為(偏頗弁済)。
- 虚偽の申告: 裁判所や破産管財人に虚偽の情報を申告する行為。
ただし、これらの事由があっても、裁判官の裁量で免責が許可される「裁量免責」が認められるケースもあります。
 (※イメージ画像)
(※イメージ画像)
自己破産の手続きにおける専門家の役割
自己破産の手続きは、多くの書類が必要で、法律的な知識も欠かせません。そのため、専門家に依頼することが非常に重要です。
1.専門家に依頼するメリット
- 手続きの代行: 自己破産の複雑な手続きを全て代行してくれます。これにより、精神的な負担を大きく軽減できます。
- 督促の停止: 依頼した時点で債権者からの督促が止まるため、取り立てに悩む日々から解放されます。
- 正確な書類作成: 必要書類の収集から、裁判所に提出する申立書の作成まで、専門家が正確に行います。これにより、手続きがスムーズに進みます。
- 免責不許可事由への対応: 免責不許可事由がある場合でも、専門家が裁判官に事情を説明し、免責が認められるよう尽力してくれます。
2.専門家を選ぶ際のポイント
- 相談実績: 債務整理の実績が豊富な専門家を選びましょう。
- 費用: 事前に相談費用や着手金、報酬について明確な説明があるか確認しましょう。
- 信頼性: 親身に話を聞いてくれるか、安心して任せられるかどうかも重要なポイントです。
自己破産は、人生を立て直すための再出発のチャンスです。一人で悩まず、まずは専門家に相談し、正しい手続きの流れを知ることから始めましょう。


コメント